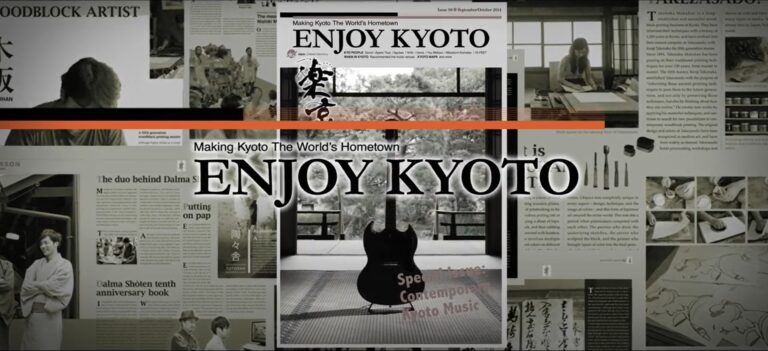大名茶人・織田有楽斎に学ぶ 楽しいが有る、という生きかた。(後編)
NHK大河ドラマ「どうする家康」の舞台にもなっている戦国時代。三英傑と呼ばれ、のちの天下人となった織田信長、豊臣秀吉、徳川家康すべてに仕え、派手な武功ではなく、聡明さと知恵によって、血で血を洗う戦乱の世をスマートに生き延びた者がいた。
織田有楽斎。この歴史に埋もれた才人は、いまでこそその名を知る人は少ないが、織田信長の弟、建仁寺塔頭・正伝院の中興の祖、さらには茶道有楽流を興した大茶人など、多種多様な顔を持つ異能の人でもあるのだ。
そこで4月22日〜6月25日まで京都文化博物館で開催されている「四百年遠忌記念特別展 大名茶人 織田有楽斎」にあわせて、織田有楽斎の謎に満ちた生涯と、彼が身を寄せた正伝永源院の歴史、そこから読み解ける現代人へのメッセージなどについて、有楽斎没後400年の記念の年に24代目住職の就任した真神啓仁氏のお話を交えつつ、紐解いていきたい。
織田家の血統、細川家の忠義、真神家の使命
織田家の地を守り生き延びた有楽斎が再興した正伝院と、細川家の菩提寺として大切にされてきた永源庵。ふたつのお寺が明治時代に合併して誕生した正伝永源院は、真神氏の曽祖父にあたる真神浄遠氏が住職に就任したあと、そこから祖父・峻巌氏、父・仁宏氏と受け継がれ、真神家は織田有楽斎、細川家双方がもたらした歴史への貢献を後世に受け継ぐ使命を果たしてきた。そして昨年、真神啓仁氏が24代目住職として就任。それは奇しくも昨年は織田有楽斎没後400年となる記念の年でもあった。真神氏は有楽斎の数奇な生涯や、正伝院・永源庵の合併、廃仏毀釈と寺宝の流出など、お寺の歴史を振り返りながら「運命の導きのようなものを感じた」と話す。

真神氏は2004年から副住職として住職である父・仁宏氏のもとで、さまざまな役割を果たしていたこともあり、住職になったからといって、自分自身の為すべきことや日々の行いにとくに変化があるわけではないと話す。しかし住職となったことで、自分の判断や行動がそのまま歴史ある寺の決断や行動とイコールになる。その責任の重さは感じるようになったといい、今回あらためて父の偉大さを知ることになったという。ではいったい彼は、いつ、どのようにして僧侶として生きる道を選んだのか?子どものころや修行時代の話を伺った。
真神氏「子どものころは家がお寺というだけで、生活そのものは一般の小中学生となんら変わるところはありません。父も将来は僧侶になれとかお寺を継げと強要したことは一度もなかったですし、すべて子どもに任してくれていたと思います。ただ、やはりふだんから父の背中を見て育つわけで、父がいつもお寺に尽力している姿を見ていると、次第に自分もやってみたいなと思うようになっていきました。またそう思わせてくれる父だったとも思います」
長男だったこともあり、子どものころからいずれ自分は僧侶になり、このお寺を継ぐことになるのだろうと、なんとなくは考えていたという真神氏。花園大学を卒業すると、すぐに建仁寺の修行道場で修行に入った。いよいよ正式に僧侶になる道を進み始める。
修行道場では、毎朝4時に起床。朝の読経にはじまり、それが終わると掃除、そして食事と続く。朝の食事はお粥のみ。禅寺では食事つくるのも修行の一環である。その後は坐禅。ときには托鉢のために街へ出て練り歩くこともある。昼食は麦飯とお味噌汁と野菜一品。午後からは掃除や薪割りなどの作務をこなし、夕方5時ごろにふたたび座禅をする。禅寺では午後には食事を取らない決まりであるため、夜は薬石という薬の代わりとしてお味噌汁と麦飯をいただき、9時には消灯となる。ただしほとんどの修行僧はそこからさらに深夜12時ごろまで「夜坐」と呼ばれる夜の坐禅をすることになっている。このような生活が毎日繰り返される。個人の自由時間はほとんどなく、禅寺ゆえ修行は多くの寺院と比べても、いたって厳しいものとなる。

真神氏「修行に入る前と後では感性が一変し、五感が研ぎ澄まされたのが自分でもわかりました。同じ景色を見ても修行前とはまったく見えかたが違っていました。空、雲、川、花。なにを見ても、すごく新鮮に見えてくる。フィルターがないまっさらな綺麗な状態で、景色や人の美しさダイレクトに飛び込んでくるようになりました。そのためか、とくに人との接しかたが変わりました。過酷な修行を経たことで、これまで以上に人の優しさがすごく大切なもの、美しく愛おしいものとして感じられるようになったのだと思います」
ただそこに座り、庭の木々や花を眺め、鳥の声に耳を澄ます
道場での修行を終えた真神氏は、正伝永源院に戻る。そして父のもとで副住職を務めたあと、昨年24代目住職として正伝永源院を継承した。現代を生きる僧侶として由緒ある寺を守っていかなければならない。またそれと同時に「有楽流」という武家茶道の一大流派を受け継ぐ家元として、茶の湯の道を究め、広めていくこともまた、自分に課せられた使命だと感じている。真神氏は自らに与えられた使命を果たすべく、定期的に座禅会や茶会を催し、来訪者に「無」になる時間を持つことの大切さを語りかけてきた。

真神氏「座禅会などでいつもみなさんにお話するのは、1日のどこかでケータイを忘れる時間を持ってくださいということ。現代の生活スタイルはつねに情報を追いかけ、また逆に情報に追われてしまっている。だから私にできることは「なにもしない時間」を提供すること。それが座禅とお茶です。お庭を眺め、たたぼーっと座る。あるいはひとつのお茶を囲んで、静かに座ってゆっくりといただく。私はいまやなにもしない時間こそが、なにより贅沢なものだと考えています。といっても、ふだんの生活空間ではなかなか本当になにもしないというのは難しいもの。ですからお寺に来ていただいて、お庭を眺め、お茶を飲み、鳥の声に耳を傾け、風の匂いを吸い込む。そういう、ただ座るだけの時間を持ってもらうこと。それこそ、とくに京都のお寺が果たせる役割なのではないかと考えています」
弱き者どもの強さ、重なる数奇な運命、現代へのメッセージ
「なにもしない時間」といえば、ゆっくりと絵画を鑑賞することも、それに近しい行為といえるだろう。お寺には多くの絵画や仏像、書や器などの芸術作品が所蔵されており、お寺を訪ねる際の楽しみのひとつでもある。正伝永源院にも多くの寺宝が所蔵されているが、通常は非公開のものも多く、また秋と冬の特別公開以外お寺そのものが非公開となっている。しかし今回、有楽斎没後400年を記念した展覧会「四百年遠忌記念 大名茶人 織田有楽斎」が開催されることとなり、ふだんあまり見ることができないさまざまな文化財を間近に見ることができる貴重な機会となっている。
とりわけ注目度が高いのが、狩野山楽が描いたとされる襖絵「蓮鷺図襖」。16面からなる大作で、金碧の背景に白い蓮の花と青々とした葉、そこに白い鷺と黒い燕が配され、16枚の襖絵の中に四季の移ろいが表現されている名品である。



真神氏「この襖絵を描いた狩野山楽は、もともと秀吉についていたとされる絵師でした。江戸時代に入り、徳川の世に移るに際して、秀吉側ついていた人間の多くが処罰されることになり、狩野山楽も豊臣型の残党との嫌疑をかけられていきます。しかし、その窮地から救うべく九条家らとともに尽力したのが有楽斎でした。狩野山楽はそのお礼にとこの襖絵「蓮鷺図襖」を収めたといわれています。つまりここでも、有楽斎は人と人との間を取り持つ役割を果たしている。もしかしたら有楽斎がいなければ、狩野山楽はここで命を落とし、この作品も描かれていなかったかもしれないのです」
失いかけた命を救われた狩野山楽。有楽斎と同じく、時代の激流に翻弄されながらも生き延びた人ならではの、儚くも優しい心情が伝わってくる繊細な作品である。
そのほかにも、同じく狩野山楽が描いた「織田有楽像」や織田有楽自作の茶杓「落葉」、さらには織田有楽斎自筆の書状や愛用の茶道具の名品などを通じて、織田有楽斎の人となりに迫る企画展となっている。
今回の展覧会は有楽斎の没後400年を記念してのもの。この節目の年に真神氏は24代目住職に就任したというのは先ほども紹介したが、もうひとつ数奇なる運命が手繰り寄せられることになった。それは先の廃仏毀釈運動で流出した宝物のひとつで、有楽斎が茶道の師と仰いだ武野紹鴎の供養塔が戻ってきたことだ。もともとこの供養塔は武野紹鷗の25回忌に今井宗久が堺に立てたものだった。しかし今井宗久(冬の陣で有楽斎が命を救った今井宗薫の父)が亡くなると有楽斎はどうしてもあの供養塔を譲り受けたいと懇願し、ぜんぶで数トンになる巨大な石塔を堺から正伝院へと運ばせたという。有楽斎は自分の墓はこの供養塔に似せて建ててほしいと遺書にしたため、実際にそっくりに建てられていることからもその敬愛ぶりがわかる。しかし明治の廃仏毀釈で流出。関西財閥の藤田家に買い取られ、大阪網島町にある太閤園の敷地内に移設されたのだった。しかし一昨年、太閤園は営業を終了。敷地売却に伴い、もとの所有者である正伝永源院へと返されることになったのだった。

真神氏「現在この供養塔は庭の中央に建っていますが、建物の奥にある有楽斎の木像と向かい合うように配置させてもらいました。だから、なにより有楽斎がいちばん喜んでいると思います。だからやはりこの供養塔の帰還が、今回の展覧会を開くひとつの大きな動機になったと思いますし、これをきっかけに失われた寺宝が、ふたたび元の場所に安置される日が訪れることを願っています」

今回の展覧会のキャッチコピーを考えるにあたって真神氏は、有楽斎が仕えた三英傑にちなみ、「鳴かぬなら 生きよそのまま ホトトギス」という有楽斎の生き様を表す句を詠んだ。「逃げの有楽」と揶揄され、着せられた汚名をなんとか払拭したい思いからだ。
激動の戦国時代、激しく命を燃やし、武士らしく戦に殉じて死を選ぶほうがむしろかんたんだったのではないだろうか。しかし有楽斎は、死が名誉だった時代、誰もが死に様を考えていた時代に、自分の意思を貫き、織田家の血を守り抜くために生き延びた。生き延びて、心静かに文化の楽しさに没頭することを選んだ。今回の展覧会は、その生き様にふれることでもあるのだ。そしてその生き様を通じて有楽斎は、居住まいを整え、時流に流されることなく心静かに日々を生きることの大切さを、400年の時を超え、同じく激動の現代だからこそ私たちに伝えようとしている。